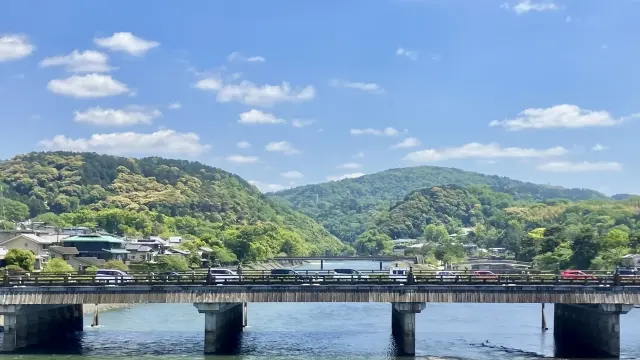人口減少・地域課題の複雑化に伴い、行政と市民・民間企業のあいだをつなぐ「中間支援組織」の重要性が増しています。
まちづくり会社と言われたり、法律に基づくものは、都市再生推進法人、地域再生推進法人といったものもあります。
こうした組織は、立ち上げ当初から永続的なモデルができあがっているわけではなく、地域に根差しながら、段階的に自立した組織へと成長していく必要があります。
以下は、実際の中間支援組織がたどる私の考える「成長ステップ」です。
自治体としては、このプロセスを理解しつつ、組織を甘やかさずに成長を促す微妙なバランスが大切かと思います。
ステップ1:行政からの委託や制度活用による立ち上げ
中間支援組織の立ち上がりは、多くの場合、行政からの委託事業や地域おこし協力隊の受け皿として始まります。
この時期は、どうしても自治体からの財政的依存が大きくなります。
この段階では「委託に甘んじず、いずれは自立する」という意識づくりが非常に重要です。
委託が永続することはなく、また委託事業だけでは柔軟な地域課題対応が難しい場合もあります。
自治体としても、単なる委託先ではなく、地域で今後もあり続けるパートナーとしての接するのが大切かと思います。
ステップ2:地域内での民間事業の模索・実践
次の段階では、委託に依存しない収益構造を模索すべく、地域内での民間事業に取り組み始めます。
これは、飲食や商品開発、シェアスペース、ワーケーション企画、民泊など、地域資源を活かした小さな実践からスタートします。
この段階は「とにかく数をこなす」フェーズです。
失敗も多いですが、ここで得られる経験がその後の事業モデルの確立につながります。
自治体の補助制度や空き物件の紹介など、挑戦を後押しする公式、非公式の支援も大変ありがたいと思います。
ステップ3:他地域・都道府県への展開
地域内で一定の成果や評判が生まれると、他地域や都道府県からも事業依頼や協力要請が入るようになります。
これは中間支援組織が「外貨を稼ぐ」フェーズです。
ここで得た資金やノウハウを、再び地元に還元する流れをつくることで、地域にとっての価値がさらに高まります。
また、地域の自治体職員が他の自治体とのネットワークで地元の中間支援組織を紹介するなど、外部へのPRも大きな力になります。
自治体への口コミは自治体職員からのものが一番ですので、そういった後押しというのは強いと思います。
制度や補助金については自治体にしか入ってこない情報もあるので、これを使ってみませんかといった声掛けも大変ありがたいと感じています。
目指す姿:自立・外貨・還元の循環モデルへ
このように、中間支援組織は
- 自治体委託による立ち上がり
- 地域内での挑戦と収益化
- 外貨の獲得と地域還元
というステップを経て、持続可能な組織へと成長していくのではないかと考えています。
最終的には、行政からの事業依存を脱し、民間事業ベースで自立した収益を上げながら、その利益を地域に再投資する構造が理想です。
まちづくりに関する非営利的な事業を行っている中で、それが行政方針と合致することで、新たな委託事業が生まれるということもあるでしょう。
しかし、それを委託事業のままに留めていてはいつまでも税金に頼ることになってしまうので、いかに収益化するかということに取り組む機会が与えられたととらえ、事業化に取り組む姿勢が必要です。
話は変わりますが、委託事業という点では、すでに行政は様々な事業を民間に委託に出しています。
中間支援組織が担うべきものは、これまでは地域外の事業者が担っていた事業、もしくは新たにスタートする事業がメインになるかと考えています。
これは、外にお金が流出してしまうものを地域内に残すことを意識し、そのために人材を育成していくといった視点ですね。
そういった役割を私はエージェント機能と言っていますが、これが果たせるようになると地域は強くなるのではないかと思います。
中間支援組織は、行政の足りないところを補うだけの存在ではありません。
行政でやるのは大変だから、収入にもなるし、中間支援組織にやってもらおうといった考えだけだと、長期的な関係継続は難しくなるのではないかと思います。
ともに未来を描き、一緒に目指していく。
そういったスタンスを継続できると良いと思います。